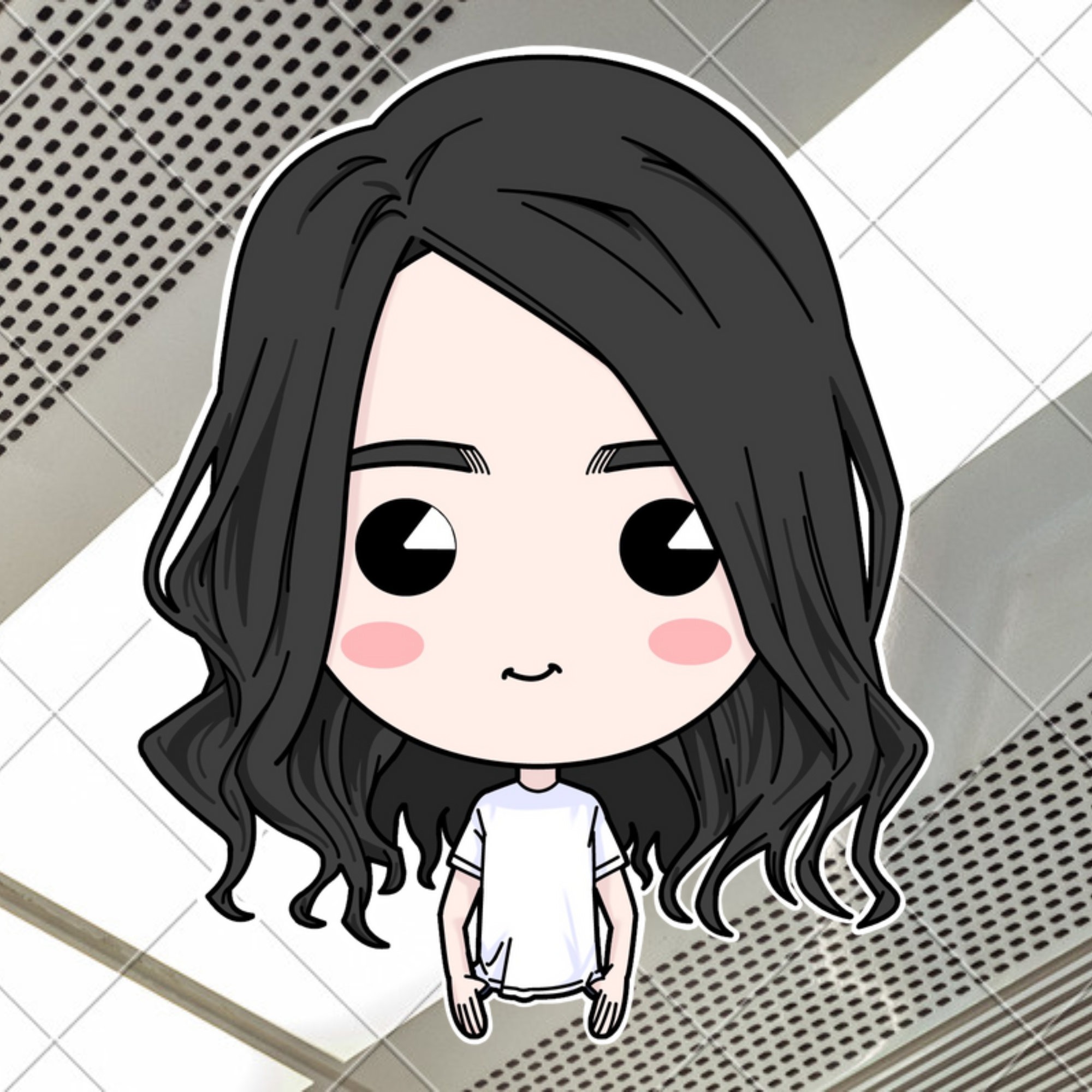「うちの子、ちょっとしたことで自信をなくしてしまう…」
「もっと自己肯定感を育てたいけど、どう接すればいいのか分からない…」
そんなふうに感じている親御さんも多いのではないでしょうか。
子どもの自己肯定感は、将来の人間関係や挑戦する力にも深く関わる大切な土台です。
でも実は、日々のちょっとした親の接し方が、子どもの心に大きく影響を与えていることをご存じですか?
この記事では、子どもの自己肯定感を育てるために親ができる接し方を7つに厳選してご紹介します。
どれも今日から実践できる内容なので、子どもの変化を少しずつ実感できるはずです。
Contents
自己肯定感 子どもとは何か?
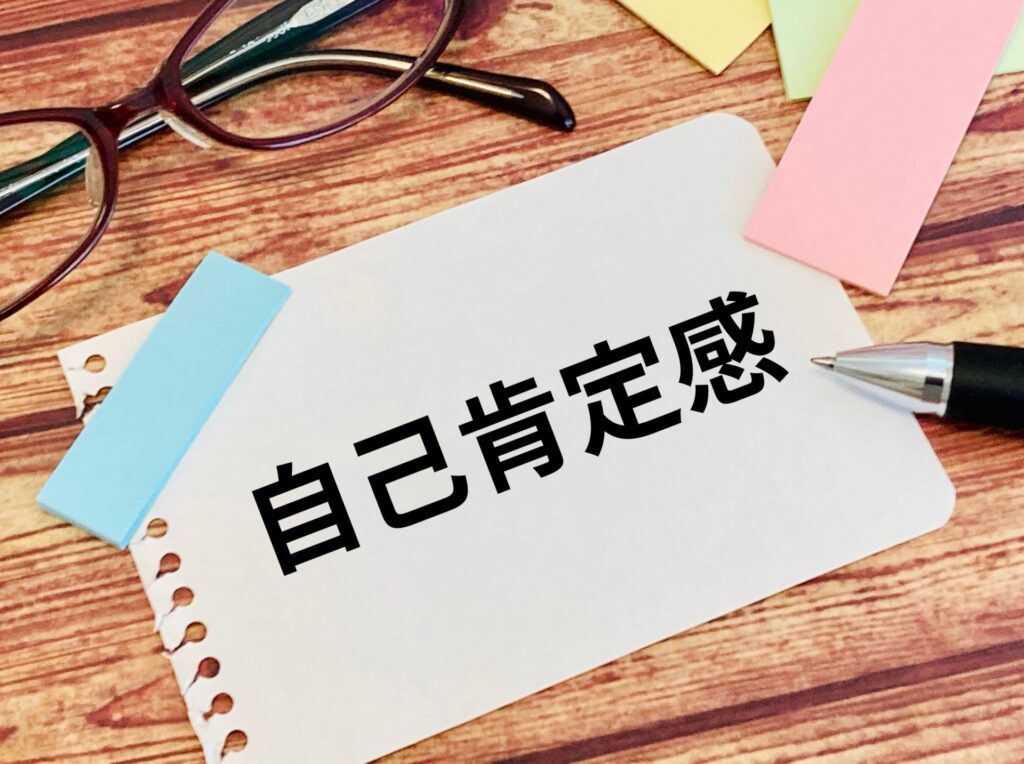
「自己肯定感ってよく聞くけれど、結局どんな意味なの?」
そんな疑問を持つ方も多いかもしれません。特に子どもの成長にとって、自己肯定感はとても大切な力です。
この章では、自己肯定感の意味をやさしく解説しながら、子どもにとってどんな影響があるのかを具体的にお伝えします。
自己肯定感の意味をやさしく解説
自己肯定感とは、「自分には価値がある」「自分はこれでいい」と思える気持ちのことを指します。
小さな子でも、自分のことをどう感じているかは行動や言葉に表れます。
たとえば、絵を描いて「見て見て!」と笑顔で持ってくる子は、「自分のやったことには意味がある」と感じている証拠です。
逆に、「こんなのダメだよね…」と自分から作品を下げてしまう子は、自信が持てず、自分を認められていない可能性があります。
【自己肯定感がある子どもに見られる行動】
- 失敗しても「次がある」と考えられる
- 自分の意見を伝えることに抵抗がない
- 他の子と違っていても「これが自分」と思える
自己肯定感は、生まれつきではなく育てていくものです。
家庭や学校など、まわりの大人の関わり方によって大きく左右されます。
【参考】ベネッセ教育情報サイト「自己肯定感とは?意味や高め方」
https://benesse.jp/kosodate/202102/20210210-1.html
子どもの成長にどう関係するの?
子どもにとっての自己肯定感は、心の土台になります。
高い自己肯定感を持つことで、さまざまなことに前向きに取り組む気持ちが生まれます。
たとえば…
- 勉強がうまくいかなくても「もう一度やってみよう」と思える
- 友だちとけんかしても「自分の気持ちを伝えてみよう」と行動できる
- 新しいことに「やってみたい」と興味を持てる
反対に、自己肯定感が低いままだと…
- 間違えたくないから挑戦しない
- 友だちの言葉を気にしすぎて疲れてしまう
- ほめられても素直に受け取れない
このように、自己肯定感は子どもの行動や人間関係に強く影響します。
毎日の声かけや関わり方で少しずつ育てていけるものだからこそ、親として意識しておきたいポイントです。
自己肯定感 子どもが低いとどうなる?

自己肯定感が低い子どもは、自分に自信を持てず、ささいなことでも大きな不安を感じやすくなります。
そのまま放置してしまうと、心の元気が失われ、将来にも悪影響を及ぼす可能性があります。
ここでは、自己肯定感が低いときに見られるサインや、そのままにしておくとどうなるかを具体的に見ていきましょう。
自己肯定感が低いときに見られる行動の裏には、親の無意識な関わり方が影響している場合もあります。
心当たりがある方は、ぜひこちらの
知らないと損する!親が陥る子育て失敗の6つの真実
もご覧ください。
よくある行動やサインの例
自己肯定感が下がっているとき、子どもはこんな行動を見せることがあります。
【よくあるサイン】
- 「どうせできない」と口にする
- すぐに「ごめんなさい」と謝るクセがある
- 褒められても「そんなことない」と否定する
- チャレンジする前からあきらめる
- ミスに対して過剰に落ち込む
たとえば、テストで少し点数が悪かっただけで「もう勉強なんてしたくない」とふてくされる子は、失敗=自分の価値が下がることと感じているかもしれません。
こうしたサインを見逃さず、早めに気づいて声をかけることが大切です。
放っておくとどうなる?
自己肯定感が低い状態をそのままにしておくと、次のような問題が起こる可能性があります。
【考えられるリスク】
- 何事にも消極的になりやすい
- 他人の顔色ばかりうかがってしまう
- 他人の評価に依存しやすくなる
- 思春期に入ると自分を否定する傾向が強くなる
例えば、友達とトラブルが起きたときに「どうせ自分が悪いんでしょ」と思い込んでしまう子は、自分の考えや感情よりも他人の意見を優先してしまう傾向があります。
自己肯定感は、大人になってからも人間関係や仕事への姿勢に影響を与えるとされています(※日本財団「18歳意識調査」より)。
だからこそ、早い段階で子どもの心に寄り添い、自分を認められる関わり方が求められるのです。
【参考】日本財団「18歳意識調査(第36回)」
https://www.nippon-foundation.or.jp/journal/2021/61999.html
自己肯定感 子どもを育てる接し方7選

子どもの自己肯定感は、日々のちょっとした声かけや態度で少しずつ育っていきます。
ここでは、すぐに取り入れられる7つの接し方をご紹介します。
① できたことを具体的にほめる

「すごいね」だけではなく、“なにが”すごいのかを具体的に伝えることが大切です。
【例】
×「えらいね!」 → ○「最後までプリントに取り組んだのがえらいね!」
このように具体的に伝えることで、子どもは「自分の行動が良かったんだ」と理解できます。
「結果よりも過程を認める」ことが、自己肯定感の土台になります。
② 小さな挑戦も応援する
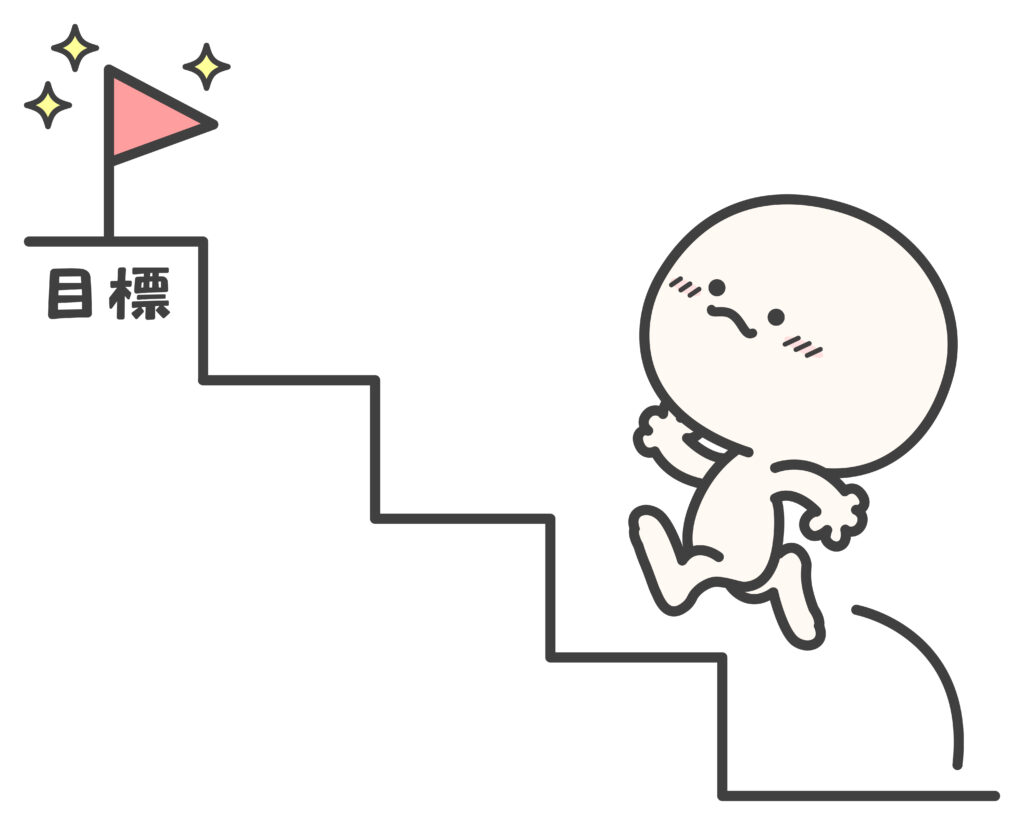
子どもが「やってみたい」と言ったことに対して、すぐに「無理だよ」と否定せず、まず応援する姿勢を見せましょう。
【例】
「このパズルやってみる!」に対して
→「いいね、どこから始める?」と聞いてあげる
うまくいかなくても、「挑戦しようとしたこと」を認めてあげることで、失敗を恐れない心が育ちます。
③ 否定せず気持ちを聞く
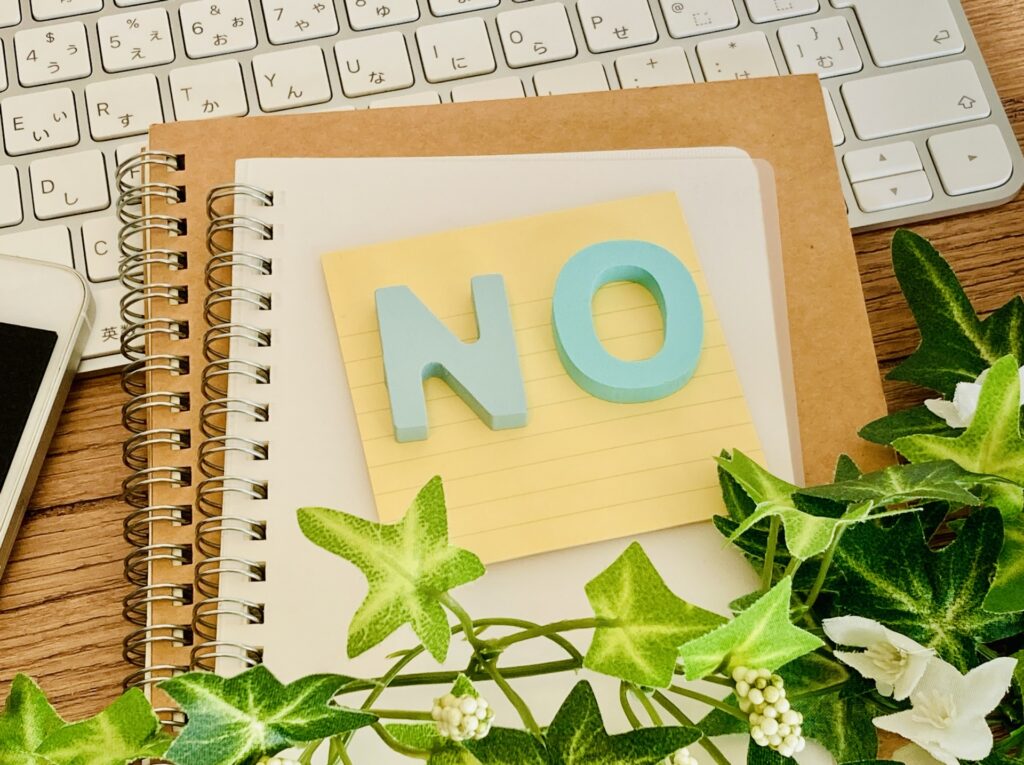
「そんなことで泣かないの!」という言葉は、子どもの感情を否定することにつながります。
【OKな返し方】
- 「悲しかったんだね」
- 「そう思ったんだね」
- 「うんうん、わかるよ」
大人から見れば小さなことでも、その子にとっては大きな感情。
まず受け止めることで、自分の気持ちに自信が持てるようになります。
④ 比べず「うちの子らしさ」を見る
「お兄ちゃんはできたのに…」
「○○ちゃんはもっと早かったよ」
つい他の子と比べてしまいがちですが、これは自己肯定感を下げる大きな要因です。
【意識したいポイント】
- 比較ではなく「昨日より今日の変化」を見る
- その子自身のペースを認める
子どもは「ぼくはぼくでいいんだ」と思えると、安心して成長できます。
⑤ 「ありがとう」を伝える習慣
手伝ってくれたとき、何かをしてくれたとき、「ありがとう」と伝えることは、子どもの存在価値を肯定することにつながります。
【例】
- 「お皿運んでくれて助かったよ」
- 「元気に帰ってきてくれてありがとう」
「感謝される経験」を重ねることで、自分が誰かの役に立っているという実感が自己肯定感を支えます。
⑥ 親も失敗を見せていい
親も完璧である必要はありません。
むしろ、失敗しても立ち直る姿を見せることが、子どもにとって良い学びになります。
【例】
- 「ごめん、今日忘れてた!次は気をつけるね」
- 「失敗したけど、やってみてよかった」
子どもは、大人の言葉ではなく「姿勢」から多くを学びます。
⑦ スキンシップで安心感を届ける

ハグや手をつなぐ、頭をなでるなどのスキンシップは「あなたを大切に思っているよ」というメッセージになります。
【おすすめのタイミング】
- 朝起きたときの「おはようハグ」
- 寝る前の「おつかれさまギュッ」
ことばよりも直接伝わるぬくもりが、自己肯定感の土台を支えてくれます。
自己肯定感 子どもを伸ばす家庭の習慣

自己肯定感は、毎日の家庭の中でも自然と育まれていくものです。
特別な道具や難しい技術は必要ありません。親のちょっとした心がけや言葉の選び方が、子どもの心の支えになります。
ここでは、今日から取り入れられる2つの家庭習慣をご紹介します。
1日5分の「振り返りタイム」
子どもの自己肯定感を育てるには、「自分を振り返る時間」を持つことが効果的です。
一日を終える前に、短い時間で「よかったこと」「できたこと」を親子で話すだけで、子どもは自分を認める力が少しずつ育ちます。
【やり方の例】
- 今日一番がんばったことは?
- 嬉しかったことはなんだった?
- どんな気持ちになった?
たとえば、「漢字テストで10点アップできた」「友だちにありがとうって言えた」など、結果だけでなく気持ちを振り返ることが大切です。
この習慣によって、子どもは「自分にはいいところがある」「今日もちゃんとがんばった」と思えるようになります。
家族の会話に「肯定語」を増やす
家庭の中に「できる」「ありがとう」「うれしい」などの肯定的な言葉が増えると、自然と自己肯定感も育ちやすくなります。
【肯定語の例】
- 「そう考えたんだね、いいと思うよ」
- 「よく見てたね、それに気づけたのはすごい」
- 「いてくれるだけでうれしいよ」
反対に、「なんでそんなことしたの?」「また失敗したの?」といった否定的な言葉が多い家庭では、子どもが自分に自信を持ちにくくなります。
もちろん、すべての言葉をポジティブに変える必要はありません。
ただ、子どもが自分の存在を肯定的に感じられる空気をつくることが、安心して過ごせる家庭につながります。
自己肯定感 子どもにおすすめの本3選
本を通して、自己肯定感について子どもと一緒に考える時間を持つことも効果的です。
ここでは、Kindle Unlimitedで読める、子どもの自己肯定感を育てるおすすめの本を3冊ご紹介します。
すべて30日間無料体験の対象なので、気軽に手に取ってみてください。
子ども向けに読み聞かせできる絵本・読み物
📘 『子どもの自己肯定感を育む3つの方法』ちゅーちゃん(キノコ書房)
→ 日常の関わりの中で、どうやって子どもの心を支えればいいかが、シンプルにまとまっています。家庭での実例が多く、親子で読んでも◎
📘 『親子で自己肯定感を育てる!毎日がハッピーになる子育てメソッド』Keika Book
→ 親子で取り組める“声かけ例”が豊富で、「どんなふうに話せばいいの?」がわからない方にもおすすめです。
📘 『笑顔あふれる子育ての成功法則』マリナー久子
→ 失敗しながらも子どもと向き合う大切さを描いた1冊。実践しやすい考え方が多く、落ち込んだときの心の支えにもなります。
📚 Kindle Unlimited は初回30日間無料体験あり!
本を買う前に中身をしっかり試したい方にぴったりです。
👉 [Kindle Unlimited 30日間無料体験はこちら]
今日からできる!まず1つ実践しよう
「すべてを一気に変えなきゃ…」と思うと、疲れてしまうこともあります。
大切なのは、ひとつでも“やってみることです。
完璧を目指さず「ひとつだけやってみる」
自己肯定感 子どもにとって、少しの変化でも親の関わり方が変わることが大きな意味を持ちます。
たとえば、今日から「ありがとう」を伝える習慣だけを始めてもOK。
明日は「比べない」を意識してみる。そんなふうに、無理なく“ひとつずつ”がコツです。
完璧である必要はありません。
「やってみた」という経験が、自分自身の親としての自己肯定感にもつながっていきます。
親自身も一緒に成長する意識で
自己肯定感は子どもだけの課題ではありません。
親自身が「自分もがんばってるな」と感じられるかどうかも大切です。
毎日の育児の中でうまくいかない日もあると思います。
そんなときは、「よくがんばった」と自分自身にも声をかけてあげてください。
親が自分を大切にしている姿は、必ず子どもにも伝わります。
まとめ|自己肯定感 子どもに必要なこと
子どもの自己肯定感は、「自分には価値がある」と思える力です。
その土台は、日々の接し方や家庭の空気の中で、少しずつ育まれていきます。
この記事でご紹介したことをもう一度ふり返ると…
- 自己肯定感とは「自分を大切に思える心」
- 否定や比較は避け、気持ちを受け止めることが大切
- 「ありがとう」やスキンシップなど小さな関わりが力になる
- 絵本や本を通じた学びも効果的
- 親自身の心のゆとりも忘れずに
どれかひとつでも、「やってみようかな」と思えることがあれば、それだけで第一歩です。
子どもの心を育てるために、できることから無理なく始めていきましょう。