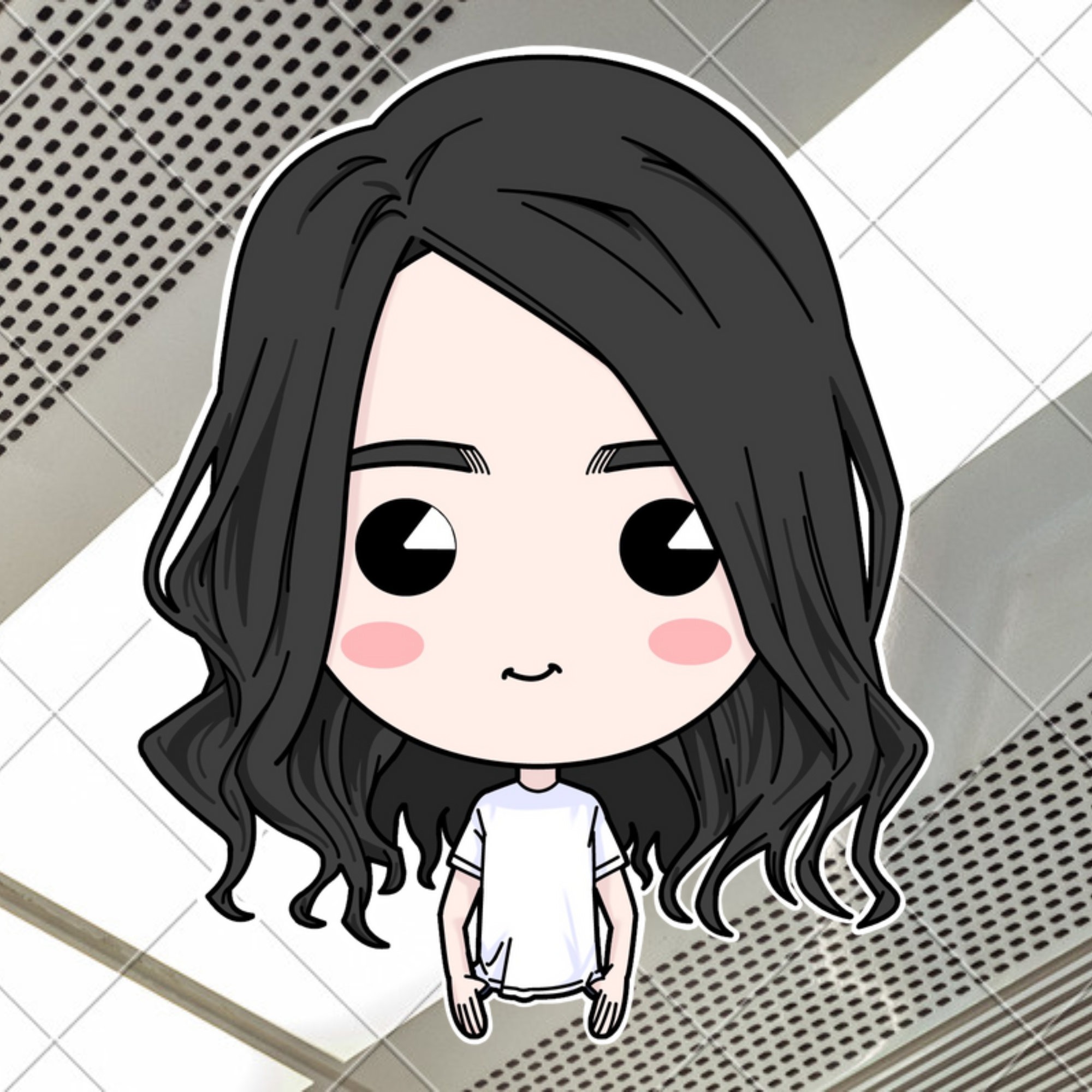「ちゃんと育てているはずなのに、自信のない様子が気になる…」
「もしかして、私の関わり方が子どもの自己肯定感に影響してるのかも…?」
子どもが自分に自信を持てなかったり、すぐに「どうせ無理」とあきらめてしまったりすると、親として不安になりますよね。
特に、小学生くらいの時期は母親との関係が子どもの“心の土台”に大きく影響すると言われています。
でも安心してください。
この記事では、自己肯定感が下がってしまう“母親のNG行動”を具体的に紹介し、今すぐできる接し方や声かけのコツまで丁寧に解説します。
僕自身も、子どもとの関わり方に悩んでいた時期がありました。
でも、ちょっとした言葉のかけ方や接し方を意識するだけで、子どもが前向きな言葉を使うようになり、挑戦を楽しめるようになったんです。
この記事を読むことで、
- なぜ自己肯定感が大事なのか
- どんな母親の言動が悪影響を与えるのか
- 今日からできる接し方のヒント
がすべてわかります。
「自信を持って育ってほしい」と願うすべての親に読んでほしい内容です。
ぜひ最後まで読んで、お子さんとの関係をよりよいものにしていきましょう。
Contents
📝この記事でわかること
- 自己肯定感とはなにか
- 親との関係が子どもの心にどう影響するか
- 自己肯定感が下がってしまうNGな言動
- 自己肯定感を高めるための接し方や声かけ
- 親自身の心の整え方と向き合い方
- KindleやAudibleで学べるおすすめ本
子どもの心を元気に育てたい、どう接すればいいか悩んでいる…
そんな方に向けて、具体例と一緒にわかりやすくまとめています。
PR表記: 本記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。
自己肯定感 母親との関係とは?

自己肯定感と母親との関係には、深いつながりがあります。なぜなら、母親の声かけや接し方は、子どもの「自分への評価」に直接つながるからです。
とはいえ、自己肯定感は母親だけでなく、父親との関わりからも育まれるものです。
家庭の中で日々どんな言葉をかけられ、どんなふうに気持ちを受け止めてもらえたか。その積み重ねが、「自分は大切な存在だ」という感覚につながっていきます。
自己肯定感ってなに?
自己肯定感とは、「自分は大切な存在だ」「自分にはできる力がある」と信じる気持ちのことです。子どもが自信を持ち、失敗しても立ち直れるようになるためにとても大切です。
例えば、テストで間違えてしまったときに「また頑張れば大丈夫」と思える子は、自己肯定感が育っていると言えます。
【ポイント】
- 自分を認める気持ちのこと
- 成績や結果に左右されずに、自分の価値を感じられる
- 幼少期から育まれる心の土台
**自己肯定感は、将来の人間関係や仕事にも大きな影響を与えます。**そのため、子どものうちから意識して育てていくことがとても大切です。
【参考】ベネッセ教育情報|自己肯定感とは?
母親との関係がどう影響するの?
自己肯定感と母親との関係には、深いつながりがあります。なぜなら、母親の声かけや接し方は、子どもの「自分への評価」に直接つながるからです。
たとえば、何かをやり遂げたときに「よく頑張ったね!」と声をかけられた子どもは、「自分は認められている」と感じることができます。一方で、失敗したときに「どうしてこんなこともできないの?」と言われると、「自分はダメなんだ」と思ってしまいます。
【母親との関係が自己肯定感に与える影響】
- 認めてもらえる経験が多いと、自信が育つ
- 否定されることが多いと、自分を好きになれなくなる
特に、小学生の頃は親の言葉を強く受け止める時期です。そのため、母親との関わり方がそのまま自己肯定感の高さや低さに表れやすくなります。
【参考】日本財団「こども1万人意識調査(2023年)」によると、
「自分にはよいところがある」と答えた子どもはわずか51.4%にとどまり、自己肯定感の低さが浮き彫りになりました。
特に日本の子どもは他国と比べて自己評価が低く、「自分が好き」と感じている割合も国際的に見て低い傾向にあります。
自己肯定感 母親との関係が崩れるNG行動5選

子どもの自己肯定感を育てたいと思っていても、無意識のうちに逆のことをしてしまっている場合があります。 ここでは、母親の関わり方で気をつけたい「自己肯定感が崩れてしまうNG行動」を5つ紹介します。
これらに心当たりがある方も、気づいた時点で関係を見直せば大丈夫です。ぜひ一緒にチェックしてみてください。
1. なんでも口出ししてしまう
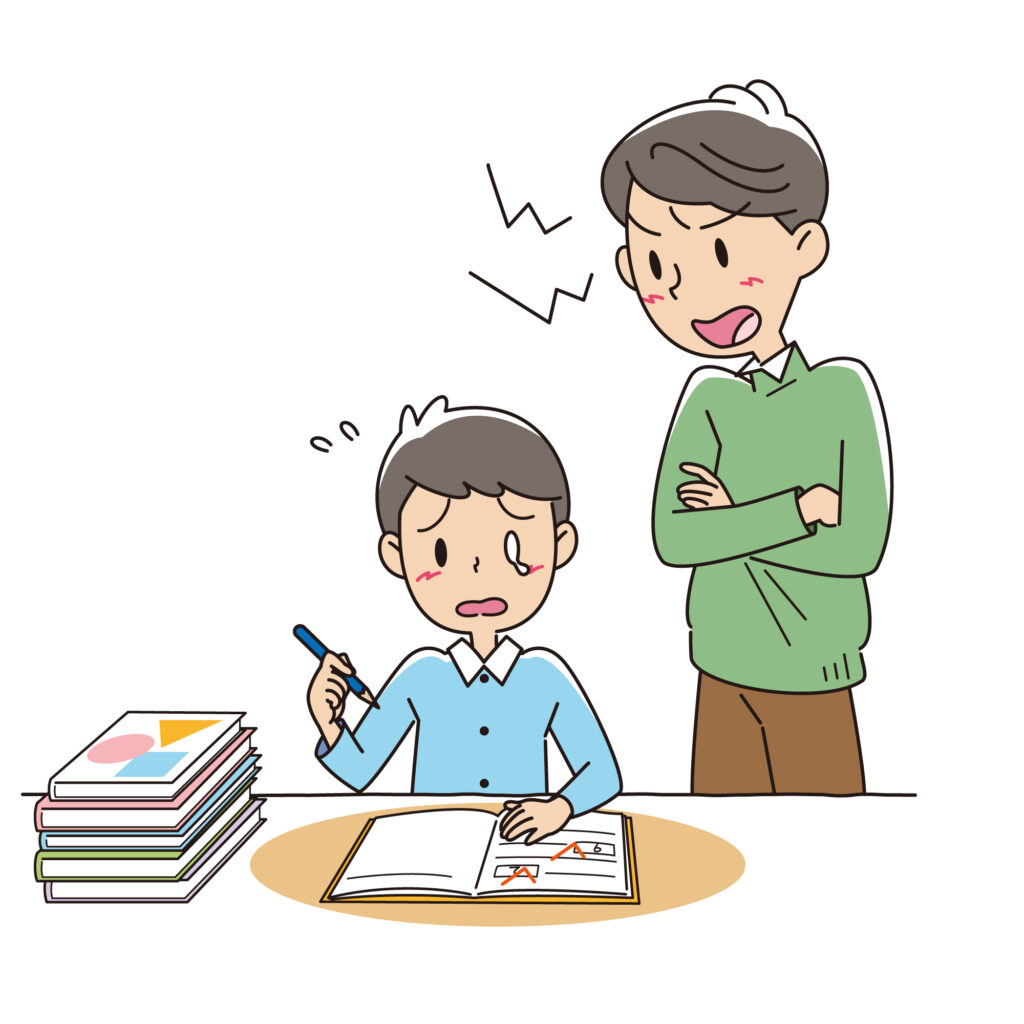
子どもが何かをしようとするたびに、先回りして口を出していませんか?
これは一見「子どものため」と思われがちですが、自分で考えて行動する機会を奪う行動です。その結果、「自分にはできないんだ」と思い込み、自己肯定感が下がってしまいます。
【口出しが多いときに起こる問題】
- 自分で判断する力が育たない
- 失敗を経験できず、成長のチャンスを逃す
- 親の顔色をうかがって行動するようになる
たとえば、宿題のやり方にすぐ口を出してしまうと、子どもは「自分のやり方じゃダメなんだ」と感じてしまいます。
見守る勇気を持ち、失敗も成長の一部として受け入れる姿勢が大切です。
2. 比べてしまう(兄弟・他の子)
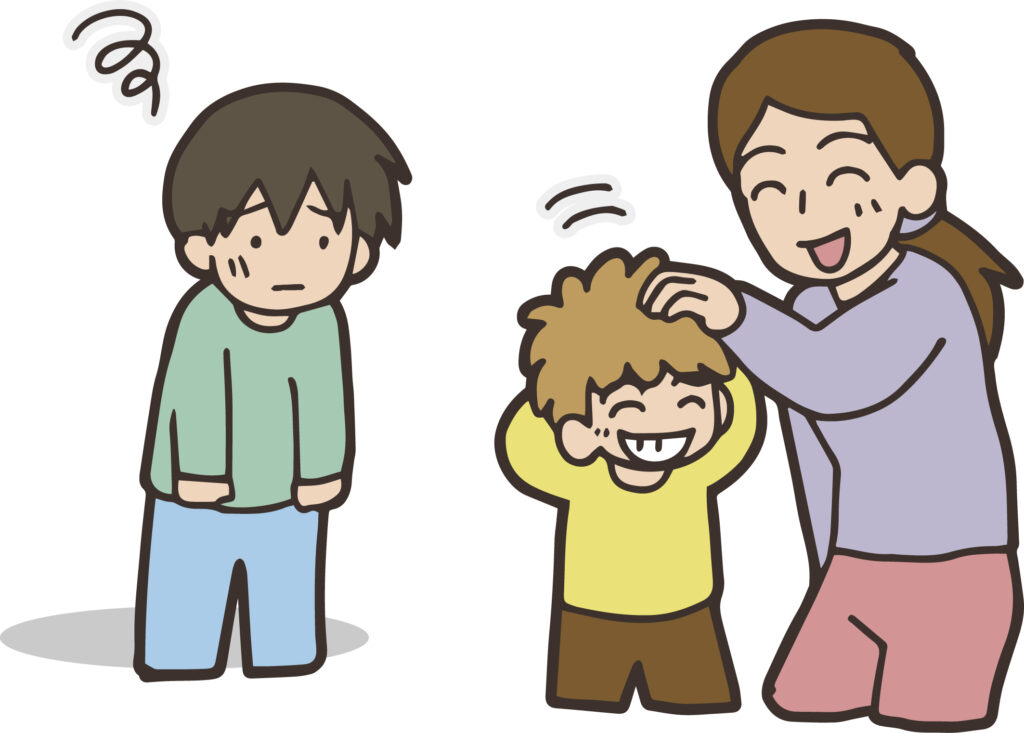
「お兄ちゃんはできたのに」「○○ちゃんはもっと頑張ってるよ」
こういった言葉は、子どもを深く傷つけ、自己肯定感を下げる原因になります。
比べられると、子どもは「自分は劣っている」「もっと頑張らないと愛されない」と感じてしまいます。
【比較が与える悪影響】
- 自分への自信をなくす
- 他人と比べて落ち込む癖がつく
- 承認欲求が強くなり、自分らしさを失う
**子どもは一人ひとり違って当たり前。**その子の「昨日よりちょっとできた」を一緒に喜ぶことが、自己肯定感を育てる近道です。
3. 「ちゃんとしなさい」が口ぐせ
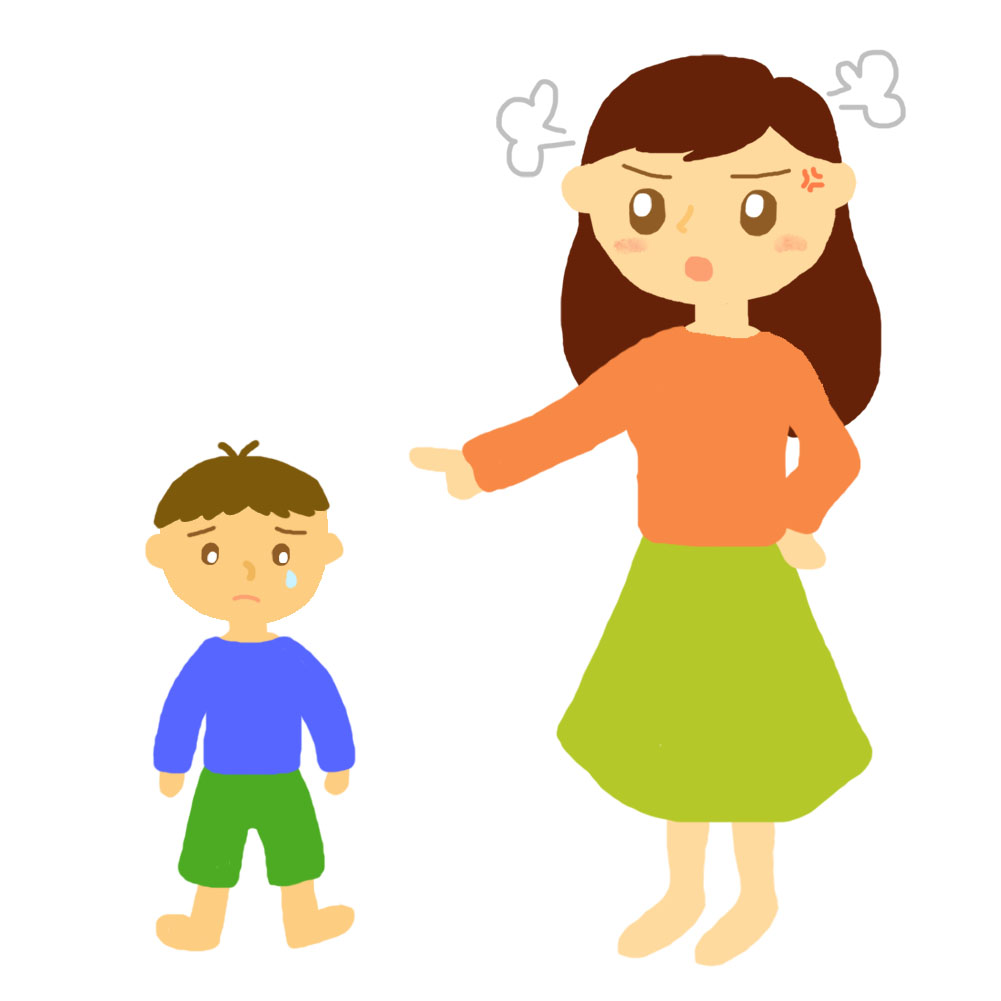
「ちゃんとしなさい」は便利な言葉ですが、何をどうすれば“ちゃんと”なのかが子どもには分かりません。
この言葉を繰り返すと、「自分はちゃんとしていない=ダメな子」と思い込みやすくなります。
【「ちゃんとしなさい」が持つ問題点】
- 抽象的で伝わりにくい
- 子どもが萎縮してしまう
- 行動の改善ではなく、人格を責められたように感じる
たとえば、「ちゃんと片づけなさい」と言う代わりに、 「使ったものを元の場所に戻してくれる?」と具体的に伝えると、子どもも理解しやすくなります。
伝え方を少し変えるだけで、子どもの受け取り方は大きく変わります。
4. 子どもの気持ちを否定する

子どもが「悔しい」「やりたくない」と言ったときに、 「そんなことで泣かないの」「わがまま言わないの」と返していませんか?
気持ちを否定されると、自分の感情に自信が持てなくなります。
【気持ちを否定することで起こること】
- 自分の気持ちを言わなくなる
- 感情を押し殺す癖がつく
- 他人の評価ばかり気にするようになる
子どもの気持ちには、まず**「そう思ったんだね」と共感すること**が大切です。 そのうえで、「どうしたいか一緒に考えよう」と声をかけることで、自己肯定感が育ちやすくなります。
5. 良かれと思って先回りする

「忘れ物しないようにランドセルに入れておいたよ」 「言わなくても分かってるから準備しておいたよ」
これらは親の愛情から出る行動ですが、子どもの自信や責任感を育てるチャンスを奪ってしまう場合があります。
【先回りしすぎるとどうなる?】
- 自分でやった達成感が得られない
- 失敗から学ぶ経験が減る
- 「親がいないとできない」と思い込む
子ども自身に「考えて行動する」経験を積ませることが、長い目で見て大切な自己肯定感の土台になります。
たとえ失敗しても、「どうしたら次はうまくいくか」を一緒に考える姿勢が、親子の信頼関係を深めます。
子どもの自己肯定感に影響を与える行動は、思っている以上にたくさんあります。
NG行動を紹介する前に、「親がついやってしまいがちな子育ての失敗」をまとめたこちらの記事もチェックしてみてください。
自己肯定感 母親との関係をよくする接し方

母親との関係を通して、子どもの自己肯定感を育てるためには、日々の接し方がとても大切です。特に小学生の時期は、親の言葉を素直に受け止めやすく、ちょっとした声かけが大きな影響を与えることもあります。
この章では、どんな接し方が自己肯定感を育てるのに効果的なのかを紹介します。すぐに実践できる内容ばかりですので、ぜひ参考にしてください。
自己肯定感を育てる親の接し方とは?
子どもの自己肯定感を育てるには、母親との関係を見直し、日々の接し方を丁寧にしていくことが重要です。
まず大切なのは、「話をしっかり聞くこと」です。子どもが何かを話しているときに途中で口をはさんだり、急いで結論を出そうとしたりしていませんか?
【よくする接し方のポイント】
- 最後まで話を聞く(うなずきや相づちも大事)
- 「できたこと」を一緒に喜ぶ
- 子どもの言葉を繰り返して共感を伝える
- 困っているときは「どうしたらいいと思う?」と問いかける
たとえば、学校で失敗したと話す子どもに「次は頑張ろうね」とだけ言うより、「悔しかったんだね。どうしたら次うまくいくか、一緒に考えようか」と声をかける方が、子どもは安心します。
**母親との関係が安心できるものになることで、子どもは自分に自信を持ちやすくなります。**その積み重ねが、自己肯定感の土台を作るのです。
【参考】子どもの自己肯定感を高める親の関わり方|ベネッセ教育情報 https://benesse.jp/kosodate/202104/20210419-1.html
親の自己肯定感が子どもに与える影響
子どもの自己肯定感は、親の接し方や言葉によって大きく左右されます。
でも、実はもっと深いところで影響しているのが、親自身の「自分をどう思っているか」という気持ち=自己肯定感です。
親が「自分はダメな親かもしれない」と感じていると、その不安や焦りが言葉や態度にあらわれ、子どももそれを敏感に受け取ります。
逆に、親が「うまくいかないこともあるけど、ちゃんとやれてる」と前向きにとらえていれば、子どもも安心しやすくなります。
この章では、親の自己肯定感が子どもにどんな影響を与えるのか、そして親自身を大切にすることの大切さについてお話ししていきます。
親の気持ちは子どもに伝わっている
子どもは、大人が思っている以上に親の気持ちをよく感じ取ります。
特に毎日一緒に過ごしている親の表情や言葉は、子どもにとって大きな影響力を持ちます。
たとえば、親が「どうせ自分なんて」と小さな声でこぼしていたとします。
それを聞いた子どもは、「大人も自信がないんだ」「失敗したらダメなんだ」と思ってしまうことがあります。
逆に、親が「失敗しても大丈夫。やってみたことが大事なんだよ」と笑顔で言えば、子どもも挑戦を恐れにくくなります。
つまり、親の自己肯定感は、子どもの考え方や行動に大きく影響しているのです。
特に小学生の時期は、まだ自分で感情をうまく整理できないことが多い分、親の表情やトーンに敏感になります。
【親の気持ちが伝わる場面の例】
- 親がため息をついている → 子どもが「怒ってるのかな?」と不安になる
- 親が前向きな言葉を使う → 子どもが「大丈夫」と思える
- 親が落ち着いて話す → 子どもも冷静になれる
だからこそ、親自身の気持ちを整えることが、子どもの自己肯定感を育てる第一歩になります。
【参考】子どもは親の“心のクセ”を映す鏡|NHK すくすく子育て(2023年5月)
https://www.nhk.or.jp/sukusuku/article/202305.html
まずは親自身が自分を大切に
子どもの自己肯定感を育てたいと思ったとき、最初に意識したいのは「親自身が自分を大切にしているか」ということです。
忙しい毎日の中で、「もっとちゃんとしなきゃ」と自分を責めてしまうことはありませんか?
でも、親が自分を否定する気持ちは、そのまま子どもにも伝わってしまいます。
たとえば、「私はダメな母親だな」と思っていると、子どもも「自分もダメな子かも」と思ってしまいやすくなるのです。
そうならないためにも、まずは自分を責めるのではなく、ねぎらうことがとても大切です。
【親自身が自己肯定感を高めるためにできること】
- 「今日はこれだけできた」と自分を認める
- まわりの親と比べない
- 「失敗しても次がある」と言ってみる
- 好きなことをする時間を少しだけでも取る
親が少しでもリラックスできる時間を持つと、自然と子どもへの言葉も柔らかくなりやすくなります。
完璧を目指さなくて大丈夫です。
自分に「よくやってるよ」と声をかけられるようになると、その安心感が子どもにも伝わっていきます。
【参考】自己肯定感を高めるために大人ができること|厚生労働省 こころの耳
https://kokoro.mhlw.go.jp/now/kokoronoe/20210712_01.html
実体験から学んだ“やってよかったこと”
母親として、実際に子どもとの関係をよくしようと試行錯誤した経験は、かけがえのない学びになります。この章では、私が実際に試して「これは効果があった」と感じたことを紹介します。
子どもの自己肯定感は、一度に大きく変わるものではありません。しかし、日々の声かけや関わり方を少しずつ変えることで、子どもの反応が変わってくるのを感じられるようになります。
母親として実感した効果的な関わり方
実際に私自身も、子どもとの関係に悩んだ時期がありました。「もっと自信を持ってほしい」「すぐに落ち込んでしまうのをなんとかしたい」と思っていたのです。
そんなときに意識したのが、次の3つです。
【実際に効果があった接し方】
- 朝「いってらっしゃい」の前に、昨日よかったことを1つ伝える
- 何かできたとき、「それ自分でやったんやな!」と事実を認める言い方をする
- 寝る前の時間に「今日一番楽しかったこと」を聞いて、最後は「ありがとう」で終わる
これを続けることで、子どもが自分の行動に自信を持ち始め、「明日も頑張ってみる」と言ってくれるようになりました。
**母親との関係は、ちょっとした習慣や声かけで大きく変わります。**完璧じゃなくて大丈夫です。少しずつでいいので、できることからやってみてください。
自己肯定感を育てたい人におすすめの本
自己肯定感について「もっと詳しく知りたい」「他の親はどうしてるの?」と感じたとき、本を読むことはとても有効な方法です。
特に最近は、スマホ1つで読める電子書籍が増えており、Kindle Unlimited(キンドル・アンリミテッド)なら対象の本が30日間無料で読み放題になります。
この章では、親子関係や自己肯定感について学べるおすすめの本を紹介します。
無料で学べる子育て本とその効果

自己肯定感についてもっと深く知りたい方には、本を通じて学ぶこともおすすめです。
特に、Kindle Unlimited(キンドル・アンリミテッド)なら対象の本が30日間無料で読み放題なので、気軽に始めやすいのが魅力です。
ここでは、自己肯定感を高める子育てに役立つ本をいくつかご紹介します。すべてKindle Unlimitedの対象書籍です。
【Kindle Unlimitedで読めるおすすめ本】
- 『自己肯定感を高める子育てのコツ』
子どもの話をしっかり聞くことの大切さや、親の言葉かけがどう影響するかをわかりやすく解説。 - 『自己肯定感アップ子育てで楽しい毎日を!』
モンテッソーリ教育を取り入れた、家庭ですぐに実践できる子どもの接し方を紹介。 - 『世界一愛されるママになるために』
母親自身の心の整え方と、子どもの自己肯定感を一緒に高めていく方法を提案。
📚👉 [Kindle Unlimitedを30日無料で試す]
また、家事や通勤中など「本を読む時間がなかなか取れない」という方には、耳で学べる【Audible(オーディブル)】もおすすめです。
📢 今なら2ヶ月間99円で聴き放題というキャンペーンも実施中なので、気になる育児書を耳から学ぶチャンスです。
育児中でもスキマ時間に学びを続けたい方には、ぴったりのサービスです。
自己肯定感 親との関係を振り返ってみよう
子どもの自己肯定感は、日々の関わり方の中で少しずつ育まれていきます。
特に親との関係は、その土台となる大切な部分です。
この記事では、自己肯定感が崩れてしまうNG行動を5つ紹介し、それに対してどのような関わり方が効果的か、実体験を交えてお伝えしてきました。
- 大切なのは、完璧な親を目指すことではなく、子どもの気持ちに耳を傾けること
- 毎日少しずつ、「見守る」「認める」「共感する」この3つを意識してみてください
そして、自分自身も学びながら子育てをしていく姿勢が、子どもにとっても安心できる環境につながります。
子どもが「自分って悪くないかも」「ちょっと頑張ってみよう」と思えるように、まずは今日からできる一歩を。
その一歩が、未来の自信につながっていきます。